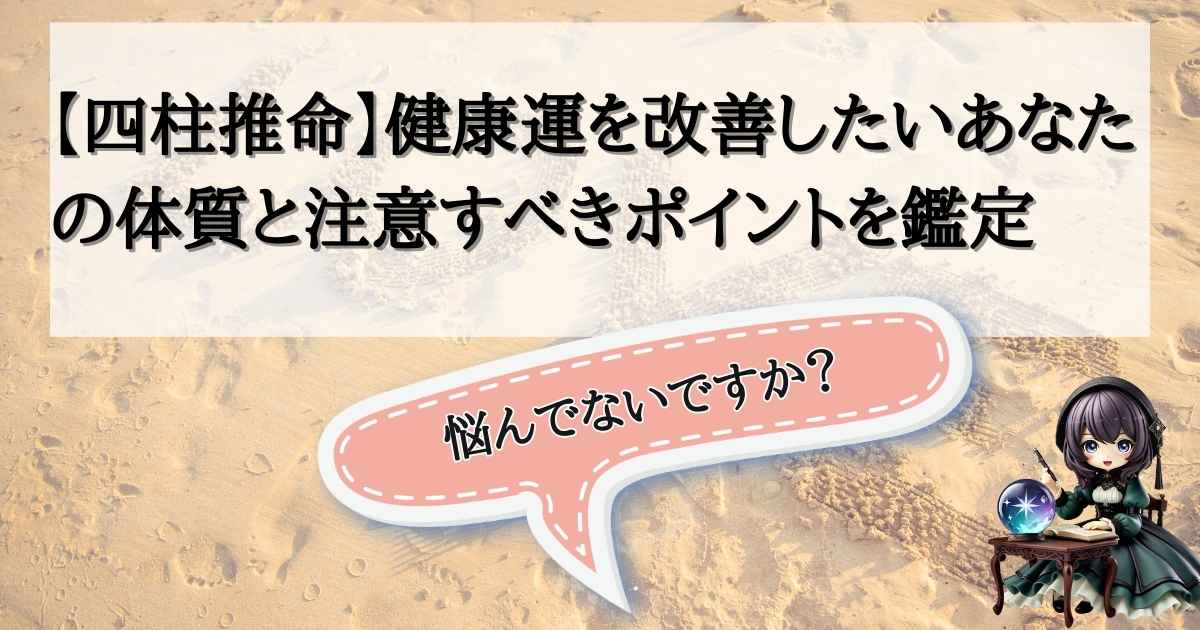【四柱推命の基礎】還暦祝いはなぜ60歳?意外と知らない「干支」の深い世界
私たちの生活に身近な「干支」。その本当の仕組みと歴史との深い関わりを探ります。
干支は12種類じゃない?「六十干支」の仕組み
「今年の干支は辰年ですね」私たちは普段、当たり前のように干支を使っていますが、その本当の仕組みをご存知でしょうか?実は、私たちが普段使う「干支」は「十二支」のことで、本来の干支は「十干(じっかん)」と「十二支(じゅうにし)」を組み合わせたものです。
十干:甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸
十二支:子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
この2つを組み合わせて「甲子(きのえね)」「乙丑(きのとうし)」…といった干支が作られます。全部で60通りあり、これを「六十干支(ろくじっかんし)」と呼びます。
還暦祝いの本当の意味は「厄除け」
なぜ還暦を60歳で祝うのか?それは、この六十干支が関係しています。生まれた年の干支は、60年経つと再び巡ってきます。例えば、「壬申(みずのえさる)」の年に生まれた人は、60歳になった時に再び「壬申」の年を迎えるわけです。
暦が還る(かえる)ことから「還暦」と呼ばれ、「赤ちゃんに還る」という意味で赤いちゃんちゃんこを着る風習が生まれました。そして、推命の世界では、この人生の大きな節目は運気が不安定になりやすいと考えられており、還暦祝いは本来、「厄除け」のための儀式だったのです。
歴史を動かす?社会変革の年
| 干支 | キーワードと歴史的な出来事 |
|---|---|
| 辛酉(しんゆう) | 「辛酉革命」という言葉があるほど、大きな変革が起こる年とされます。日本書紀によれば、神武天皇の即位や聖徳太子の憲法十七条発布もこの年でした。 |
| 甲子(かっし) | 六十干支の始まりの年。物事を始めるのに良いとされ、歴史上、甲子や辛酉の年には元号が改められる「改元」が多く行われました。 |
| 戊辰(ぼしん) | 日本では「戊辰戦争」で有名です。明治維新という大きな時代の転換期に起こった内乱でした。興味深いことに、昭和の時代が終わった1988年も戊辰年でした。 |
まとめ
干支は、単なる暦のシンボルではなく、60年という壮大な時間のサイクルを示す、先人の知恵の結晶です。ご自身の生まれた年の干支を調べてみることは、自分の運命の出発点を知ることにも繋がります。この機会に、干支の奥深い世界に触れてみてはいかがでしょうか。